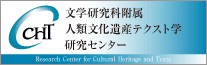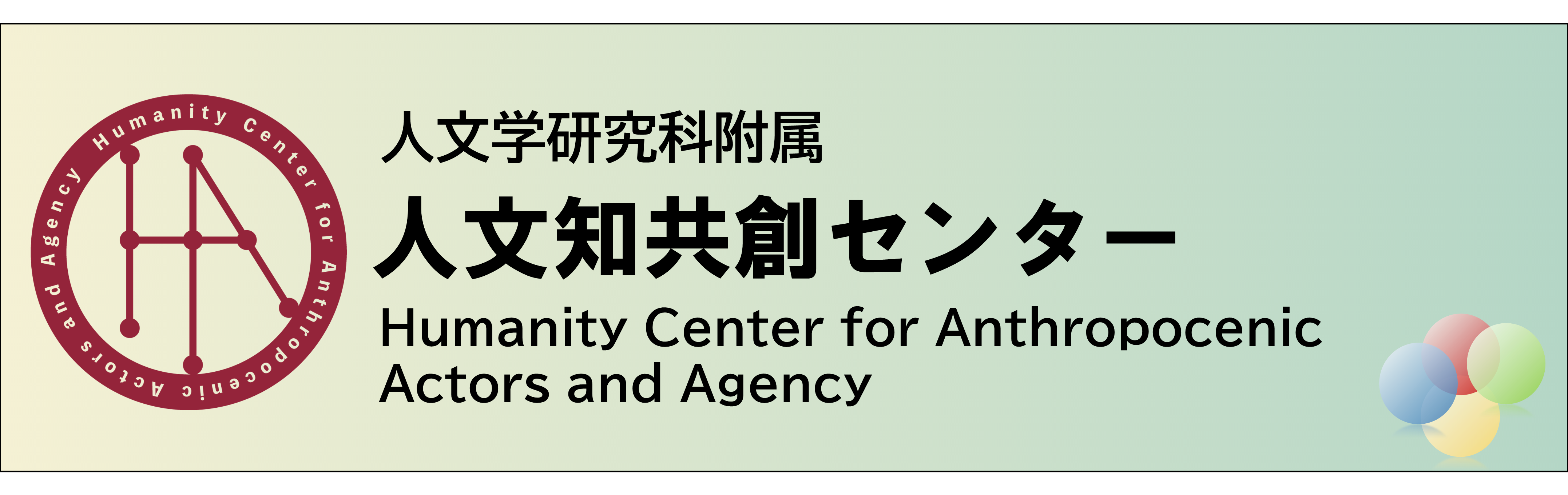哲学 Philosophy
大学院
本哲学研究室の大学院教育は、哲学史に深く根ざした専門知識の獲得と、現代社会の諸問題の本質に対する洞察力の育成を目指しています。学生は、哲学の原典や多様な言語の研究文献を扱う語学力と共に、批判的な思考と精緻な表現力を磨き上げます。それぞれの教員による指導のもと、学生は哲学各分野の特有な概念や研究方法を体系的に学び、自身の研究を深めていきます。
研究の範囲は広く、古典哲学から政治思想、規範・応用倫理にいたるまで、学生の興味に基づいたテーマに自由に取り組むことが可能です。いずれにせよ重要なのは、セミナーや研究会を通じて、研究成果を専門外の研究者にも明確かつ効果的に伝える能力を養うことです。
学生はまた、全国的な学会で研究成果を発表し、より広い研究コミュニティとの連携を図る機会に恵まれています。これにより、学外の研究者から貴重なフィードバックを受け取り、自らの研究ネットワークを拡大できます。さらに、海外留学や海外学術雑誌への論文投稿を通じて、国際的な視野を広げるサポートも提供しています。
キャリアに関しても、学内外の多様なリソースを活用し、将来のキャリアパスについての相談を行っています。学術界だけでなく、公共政策、教育、出版など、哲学研究の経験が生きる多方面でのキャリア構築をサポートします。
大学院生活は、哲学という共通の志を持つ仲間たちとの刺激的な対話と学びの場です。教員の適切な指導のもと、学生は哲学的問いを深く掘り下げ、自らの考えを発展させることができます。私たちとともに、哲学の世界で新たな地平を開拓しましょう。
担当教員
学部
多くの人が「哲学」と聞くと、難解で実用性の乏しい学問という印象を持つかもしれません。しかし、実際には哲学は、現代社会が直面する複雑な諸問題に対して深い理解と本質的な対処法を提供し得る、非常に有益な学問分野です。この学問は、批判的思考力、倫理的問題への洞察、複雑な問題の解決能力、効果的なコミュニケーション、そして自己認識と自己実現の重要性を教えてくれます。これらは、環境問題、経済的不平等、政治的対立といった、私たちが直面する多くの課題に対して、より根本的な解決策を見つけ出すために必要不可欠です。
たとえば、最近のAIの台頭は、人間とは何かという問題を社会全体で共有する契機となっています。自由意志、自己意識、感情、創造性などの人間特有の能力を機械に付与できるのか、そしてそれが可能な場合、「人間らしさ」とは何を意味するのかという問いがますます重要になっています。AIが意識や感情を持つようになれば、それに人間と同等の権利を認めるべきかどうかという問題も重要です。これらは哲学が長年にわたって取り組んできた人間性を規定する心の諸能力や倫理的規範に関する課題に深く関わっています。
私たちの研究室では、学生のみなさんが自身の興味関心に基づいて、あらゆる話題について掘り下げて探究することを奨励しています。プラトンやアリストテレスから現代の哲学者たちにいたるまでの個別の思想を追究することも、生命倫理、技術と人間、動物愛護、環境問題といった時事的話題に焦点を当てることも可能です。みなさんが自らの問題意識を持ち、自主的に学習・研究を進める過程で、あるいは学生同士との対話を通じて、問題の解決に近づけるようサポートします。この研究室では、哲学という共通の志を持つ仲間たちと出会い、互いに刺激を受け合いながら、自らの知的好奇心を深めていくことができます。私たちとともに、知の探究に挑戦しましょう。
担当教員
各学繋
言語文化学繋
英語文化学繋
文系思想学繋
超域人文学繋
歴史文化学繋
英語高度専門職業人学位プログラム
英語高度専門職業人コース
News & Events
-
2026.02.17
イベント
-
2026.02.02
教育
-
2026.01.27
入試
-
2026.01.27
入試

 布施 哲
布施 哲