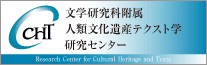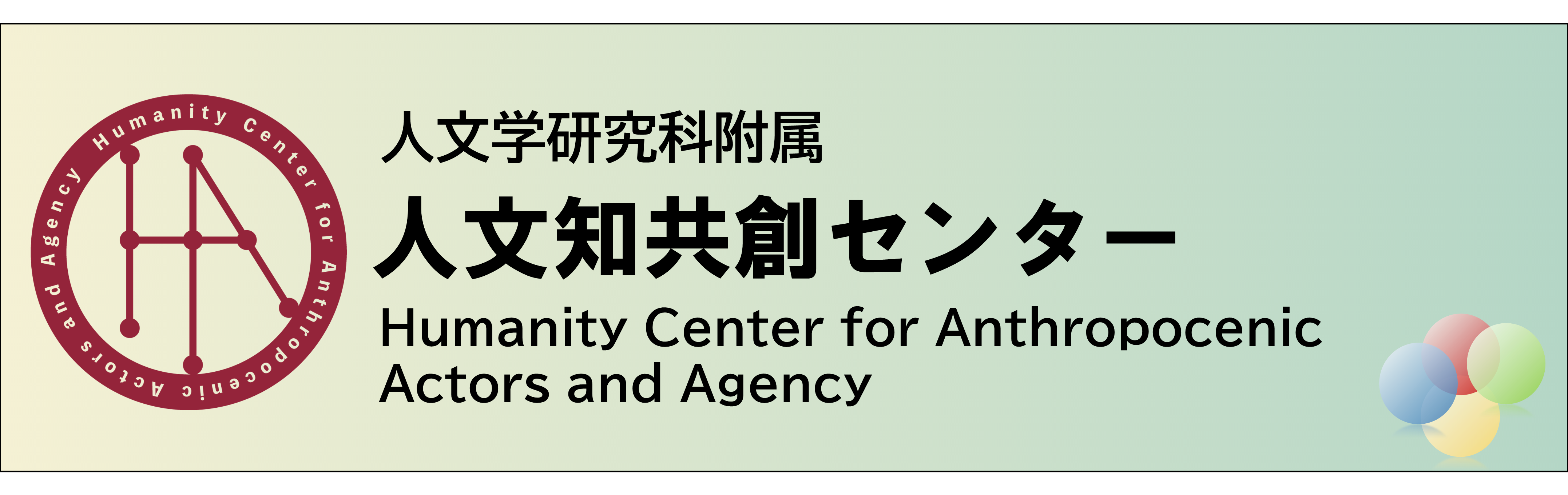人類文化遺産テクスト学研究センター メンバー
メンバー Members
周藤芳幸(センター長)
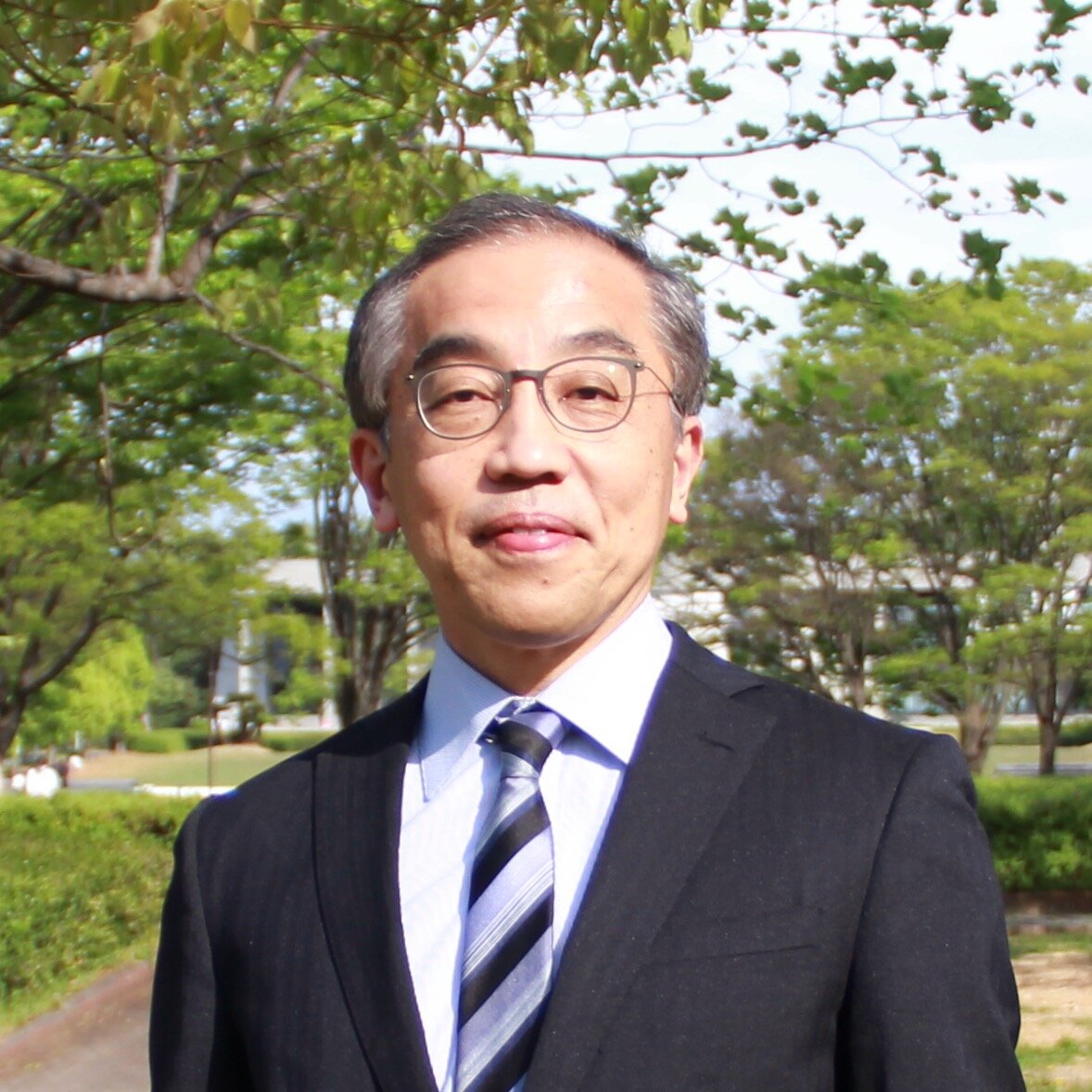
紹介文
専門はギリシア考古学、東地中海文化交流史。ギリシアでは主としてパウサニアスの『ギリシア案内記』を手掛かりとするトポグラフィや彫像文化の研究に、またエジプトではアコリス遺跡とその周辺の採石場の実地調査を踏まえてヘレニズム時代の在地社会をめぐる諸問題の解明に、それぞれ取り組んでいる。おもな著書に『古代地中海世界と文化的記憶』(編著、山川出版社、2022年)、Transmission and Organization of Knowledge in the Ancient Mediterranean World(編著、Phoibos Verlag, 2021)、『パウサニアス ギリシア案内記2 ラコニア/メッセニア』(京都大学学術出版会 、2020年)、『ナイル世界のヘレニズム ーエジプトとギリシアの遭遇』(名古屋大学出版会、2014年)、『古代ギリシア 地中海への展開』(京都大学学術出版会、2006年)などがある。
専任教員
梶原義実
紹介文
専門は日本考古学。飛鳥~奈良時代の古代寺院研究を中心におこなっている。とくに地方における国分寺の造営過程について、寺院出土の古瓦資料から実証的な分析を加えている。近年は古代寺院の立地と周辺景観を総合的に検討することで、古代の人々の寺院観・宗教観についての復原を試みている。
主著は『国分寺瓦の研究-考古学からみた律令期生産組織の地方的展開-』(名古屋大学出版会、2010年)、『古代地方寺院の造営と景観』(吉川弘文館、2017年)。
影山悦子

紹介文
専門はイスラーム以前の中央アジア文化史。とくに、「シルクロードの商人」として知られるソグド人の宗教や風俗について、壁画や葬具などの考古資料をもとに考察している。最近では、クシャーン朝期(1〜3世紀)からエフタル期(5〜6世紀)の壁画にも関心を持ち、その連続性について検討している。曽布川寛・吉田豊(編)『ソグド人の美術と言語』2011年(臨川書店)の第3章「ソグド人の壁画」を担当。
郭佳寧
紹介文
専門は中世日本の宗教文芸。院政期に活動する真言僧の思想と宗教実践の研究を中心とし、中世日本における顕密仏教を表象する重要な拠点である仏教寺院(宗教空間)の役割、及び寺院間のネットワーク、更にそれと関連する宗教者の動きを考察する。論文に「覚鑁撰「多聞天講式」考―講式をめぐる思想・信仰・伝承の生成―」(『日本宗教文化史』通巻第43号、2018年)、「『高野山往生伝』があらわす宗教世界―中世高野山信仰についての一考察―」(『説話文学研究』55号、2020年)などがある。
井上隼多
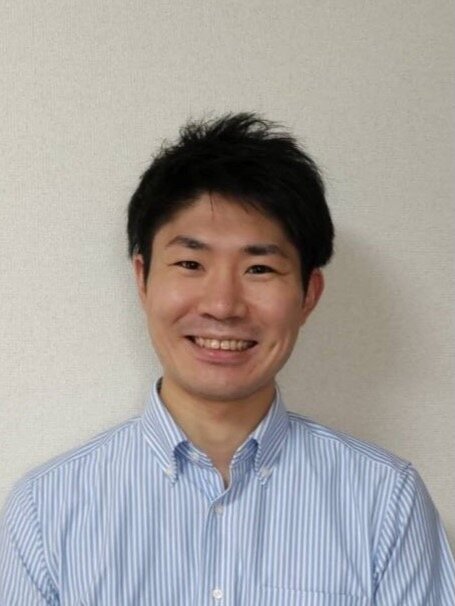
紹介文
専門は日本考古学。主に7世紀~11世紀を研究対象としており、須恵器をはじめとする手工業製品の生産と使用実態に関する調査を進めている。近年は3Dデータの利活用にも注力しており、名古屋大学大学院情報学研究科および名古屋大学博物館と連携しつつ、機械学習を応用した資料分析手法の研究や、博物館施設用の文化財3Dデータ表示アプリケーション"Culpticon(カルプティコン)"の開発を進めている。単著論文に「古代日本における陶硯の使用実態と統制」(『古代文化』第72巻第1号、2020年)、共著論文に「埋蔵文化財保護行政における3Dデータ活用―機械学習を活用した須恵器杯蓋の産地同定手法― 」(『情報文化学会誌』Vol.28, No.2、2022年)などがある。
兼任教員
佐々木重洋
紹介文
専門分野は文化人類学。熱帯アフリカおよび日本を主たるフィールドとしつつ、宗教的世界観と物質性に関する調査研究を継続している。 単著に『仮面パフォーマンスの人類学―アフリカ、豹の森の仮面文化と近代―』(世界思想社 2000年)、共編著に『「物質性」の人類学―世界は物質の流れの中にある』(古谷嘉章・関雄二・佐々木重洋(編)同成社 2017年)、『聖性の物質性―人類学と美術史の交わるところ―』(木俣元一・佐々木重洋・水野千依(編)三元社 2022年)、共著に『甦る民俗映像―渋沢敬三と宮本繋太郎が撮った一九三〇年代の日本・アジア』(宮本瑞夫・佐野賢治・北村皆雄他(編) 岩波書店 2016年)、共訳書に『神性と経験―ディンカ人の宗教―』(ゴドフリー・リーンハート著 出口顯監訳 坂井信三・佐々木重洋訳 法政大学出版局 2019年)などがある。
吉田早悠里

紹介文
専門は文化人類学。エチオピア南西部を主なフィールドとし、民族間関係やムスリム聖者崇拝についての調査を進めるとともに、21世紀初頭に同地を訪れたオーストリア人のフリードリッヒ・ユリウス・ビーバーが遺した資料群についてのアーカイヴズ研究にも取り組んでいる。単著に『誰が差別をつくるのか エチオピアに生きるカファとマンジョの関係誌』(春風社、2014年)、『 Greetings from the Austrian-Hungarian Monarchy, the Ethiopian Empire and Beyond: The Picture Postcards of Friedrich Julius Bieber (1873-1924) / Grüße aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, dem Kaiserreich Äthiopien und Anderswo: Die Ansichtskarten von Friedrich Julius Bieber (1873-1924) 』(LIT Verlag、2021年)、編著に『 Reisen nach Äthiopien: Tagebücher 1904, 1905, 1909 』(Friedrich Julius Bieber著、吉田早悠里編、LIT Verlag、2021年)、共訳書に『反政治機械----レソトにおける「開発」・脱政治化・官僚支配』(ジェームス・ファーガソン著、石原美奈子・松浦由美子・吉田早悠里訳、水声社、2020年)などがある。
川本悠紀子

紹介文
西洋古典学(古代ローマ時代の散文)・古代ローマ史、都市・建築・美術をはじめとする文化史、社会史が専門です。対象とする地域は主にイタリア半島(特にローマ、ポンペイ、ヘルクラネウム、スタビアエ、オプロンティス)ですが、小アシア(エフェソス、アプロディシアス)とブリタニア(バース、フィッシュボーン)についても研究しています。近年は、古代ローマ住宅のほかに、古代ローマにおける庭園についても研究を進めており、コーネル大学のThe Casa della Regina Carolina Project at Pompeiiにも専門家として参加・発掘にも従事していました。また、専門ではありませんが碑文のデジタル化に関するプロジェクトEpiDocの日本での情報提供・ワークショップ開催、古代ローマの庭園データベース(Cornell, NYU)の作成、古典籍から天文学的現象を繙くプロジェクト、タルクィニア周辺の遺跡と道・交易との関係性に迫るプロジェクトなどにも参加しています。
研究員
阿部美香 ABE Mika
王穎 WANG Ying
共同研究員
木俣元一
紹介文
専門はヨーロッパ中世のキリスト教美術史。最近は、偶像とイコノクラスム、イメージの物質性と図像の「意味」との関係、観者の視覚経験を通じた予型論的認識(ヴィジュアル・タイポロジー)などに関心があり、並行してシャルトル大聖堂西正面を中心に初期ゴシック彫刻史に関する考察をまとめている。単著書として『シャルトル大聖堂のステンドグラス』(中央公論美術出版、2003年)、『ゴシックの視覚宇宙』(名古屋大学出版会、2013年)がある。
程永超 CHENG Yongchao
紹介文
東北大学 東北アジア研究センター 日本・朝鮮半島研究分野
専攻は前近代(17世紀~19世紀)東アジア(徳川日本・朝鮮王朝・明清中国)国際関係史と異文化交流史。韓国・日本・中国などに所蔵されている一次史料を比較検討しながら二国間関係(日本と中国)に常に第三の視点(朝鮮)を導入しつつ、具体的に細かく実証研究するとともに、グローバル・ヒストリーの手法を使って、東アジア史の再構築を実現しようとする。
浅野ひとみ ASANO Hitomi
市川彰 ICHIKAWA Akira
佐藤純子 SATO Junko
須網美由紀 SUAMI Miyuki
中根若恵 NAKANE Wakae
野澤曉子 NOZAWA Akiko
Sabrina MANCUSO
News & Events
-
2025.06.19
入試
-
2025.06.19
入試
-
2025.06.12
イベント
-
2025.06.06
イベント
-
2025.06.06
イベント
-
2025.06.03
入試
-
2025.05.28
教育
-
2025.05.23
入試